日本の首都、東京。高層ビルが立ち並び、最新のテクノロジーが息づく一方で、一歩路地に入れば、古き良き日本の面影を色濃く残す場所が数多く存在します。今回私が皆様にご案内するのは、そんな東京の喧騒を忘れさせてくれる、まるで時が止まったかのような静謐な空間、根津神社(ねづじんじゃ)です。
「東京に神社なんて、浅草寺や明治神宮くらいしか知らないよ」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、根津神社は、東京の歴史と文化を深く理解する上で、決して見逃すことのできない、まさに「隠れた名所」と呼ぶにふさわしい場所なのです。
根津神社の歴史:1900年以上の時を超えて
根津神社の創建は、今からおよそ1900年以上前、第12代景行天皇の時代にまで遡ると言われています。これは、日本がまだ神話の世界から現実へと歩み始めた、非常に古い時代のことです。
伝説によれば、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の折、この地に立ち寄り、須佐之男命(すさのおのみこと)を祀ったのが始まりとされています。その後、度重なる戦乱や災害を経て、現在の地に遷座され、江戸時代には徳川綱吉によって大規模な社殿の造営が行われました。これにより、江戸の三社(根津神社、日枝神社、神田明神)の一つとして、江戸庶民からの篤い信仰を集めるようになったのです。
特に、江戸幕府の世継ぎを願った綱吉の生母、桂昌院(けいしょういん)の祈願所となったことは、根津神社の格式を一層高めることになりました。現代まで受け継がれる壮麗な社殿は、その名残といえるでしょう。
都会のオアシス:四季折々の美しさを楽しむ
根津神社の魅力は、その歴史だけにとどまりません。境内は緑豊かで、都会の真ん中にあるとは思えないほど静かで落ち着いた雰囲気です。
- つつじの季節(4月中旬~5月上旬): 根津神社といえば、何と言っても「つつじ」です。2000株以上ものツツジが咲き誇る境内は、まるで絵画のように鮮やか。この時期には「文京つつじまつり」が開催され、多くの人々で賑わいます。お祭りの時期でなくても、静かに散策するだけでも、その美しさに心を奪われることでしょう。
- 新緑の季節(5月~6月): ツツジが終わると、今度は瑞々しい新緑が境内を包み込みます。木漏れ日が地面に模様を描き、深呼吸するたびに清々しい空気が体に染み渡ります。
- 紅葉の季節(11月中旬~12月上旬): 秋には、木々が燃えるような赤や黄色に染まります。紅葉に彩られた参道は、まるで別世界。静寂の中で、ゆったりと散策する時間は格別です。
- 冬の静寂: 雪が積もれば、白銀の世界が広がります。普段とは違う、しっとりとした神社の姿は、心を洗われるような美しさです。
知られざる見どころ:一度は訪れたいパワースポット
根津神社は、壮麗な社殿だけでなく、境内には数多くの摂社・末社が点在しており、それぞれに unique な魅力があります。
- 千本鳥居: 京都の伏見稲荷大社ほどではありませんが、根津神社にもまるで異世界へと誘うかのような、朱色の鳥居が連なる小道があります。鬱蒼とした木々に囲まれた鳥居のトンネルは、神秘的な雰囲気に満ちており、写真撮影にもぴったりのスポットです。地元の人でも、この鳥居の存在を知らない人がいるほど、隠れた名所と言えるでしょう。
- 溶岩洞窟・乙女稲荷: 千本鳥居の奥には、洞窟があります。中には小さな祠があり、商売繁盛や五穀豊穣の神様が祀られています。ひんやりとした空気と、薄暗い照明が、さらに神秘的な雰囲気を高めています。
- 武陽隠れ岩: 境内の一角には、大きな岩が鎮座しています。これは、昔、合戦から逃れる武士が隠れたという伝説が残る岩で、パワースポットとしても知られています。
- 銀杏の木: 境内には、推定樹齢700年と言われる大きな銀杏の木があります。秋になると黄金色に輝き、参拝者の目を楽しませてくれます。
参拝の作法とマナー
日本のお寺や神社を訪れる際には、いくつかの作法やマナーがあります。初めての方でも安心して参拝できるよう、基本的なことをご紹介します。
- 鳥居をくぐる: 神社の入り口にある鳥居は、神聖な領域との境界線です。鳥居をくぐる際は、軽く頭を下げて一礼しましょう。また、鳥居の中央は神様が通る道とされているので、できるだけ端を歩くのが良いとされています。
- 手水舎(ちょうずや)で身を清める: 手水舎では、参拝前に心身を清めます。
- まず、右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水を汲んで左手にかけ、清めます。
- 次に、柄杓を左手に持ち替え、右手に水をかけて清めます。
- 再び柄杓を右手に持ち、左手に水を溜め、口をすすぎます。この時、柄杓に直接口をつけないように注意しましょう。
- 最後に、柄杓を立てて残った水で柄を清め、柄杓を元の場所に戻します。
- 拝礼: 本殿にお参りする際は、一般的に「二礼二拍手一礼」を行います。
- 拝殿(はいでん)の前まで進み、軽く一礼します。
- 鈴があれば、鈴を鳴らします(必須ではありません)。
- 二回、深くお辞儀(二礼)をします。
- 二回、柏手(かしわで)を打ちます(右手と左手を打ち合わせます)。
- もう一度、深くお辞儀(一礼)をして拝礼は終了です。
- 神様へのお願い事をする際は、拝礼の前に心の中で唱えるのが一般的です。
服装について: 特に決まった服装はありませんが、露出の多い服や派手な服装は避けた方が良いでしょう。静かな場所なので、落ち着いた服装がおすすめです。歩きやすい靴は必須です。
アクセス方法:意外と簡単!
根津神社は、東京メトロ千代田線「根津駅」または「千駄木駅」から徒歩5分、南北線「東大前駅」からも徒歩10分と、アクセスは非常に便利です。
- 東京メトロ千代田線「根津駅」利用の場合:
- 1番出口を出て、目の前の広い通り(本郷通り)を左(谷中方面)に進みます。
- しばらく歩くと、右手に大きな鳥居が見えてきます。
- 東京メトロ千代田線「千駄木駅」利用の場合:
- 2番出口を出て、右に進みます。
- 最初の交差点を右に曲がり、しばらく進むと左手に根津神社の鳥居が見えてきます。
地図アプリの活用: 初めて訪れる場合は、スマートフォンの地図アプリで「根津神社」と検索し、ルート案内を利用するのが一番確実です。
参拝後の楽しみ:周辺散策
根津神社の周辺には、魅力的なエリアがたくさんあります。参拝の後は、ぜひ散策を楽しんでみてください。
- 谷中銀座商店街: 昔ながらの商店街で、食べ歩きやお土産探しに最適です。「夕焼けだんだん」と呼ばれる階段からの眺めは有名です。
- 谷中霊園: 緑豊かな広大な公園のような霊園で、散歩にぴったりです。著名人のお墓もあります。
- 東京大学本郷キャンパス: 赤門で有名な東京大学のキャンパスも、歩いて行ける距離にあります。歴史的な建物が多く、散策するだけでも楽しめます。
費用について
根津神社の参拝は無料です。
- 交通費: ご自宅からの交通費がかかります。東京近郊からであれば、往復1,000円~2,000円程度を見積もっておくと良いでしょう。
- 飲食費: 参拝後、周辺で食事をする場合は、ランチで1,000円~3,000円程度、カフェで500円~1,000円程度が目安です。
- お土産代: もしお土産を購入される場合は、別途ご予算をご用意ください。
- つつじまつり開催時期: つつじの時期には、屋台なども出店し、賑わいます。
日帰り旅行として: 交通費と飲食代を合わせても、3,000円~5,000円程度で十分に楽しめるでしょう。
まとめ
根津神社は、1900年以上の歴史を持つ、東京でも有数の古社です。壮麗な社殿、緑豊かな境内、そして何よりも、都会の喧騒から離れて静かな時間を過ごせるという点が、この神社の最大の魅力と言えるでしょう。
今回ご紹介した「千本鳥居」や「溶岩洞窟」は、地元の人でも知らない人がいるほどの隠れた見どころです。ぜひ、これらのスポットを巡りながら、根津神社の奥深い魅力を探求してみてください。
日本、そして東京の歴史と文化に触れたいと願うすべての旅行者にとって、根津神社はきっと忘れられない体験となるはずです。次の東京旅行では、ぜひこの「隠れた名所」を訪れてみてください。きっと、あなただけの特別な発見があるはずです。

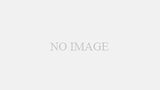
コメント